高校生海外ボランティア・セブ

2026年春・夏休み|高校生のセブ島ボランティア(1週間)
国際理解と貧困支援を体験
コロナ収束後、セブの高校生向けボランティアは2022年夏から再始動。SDGsに触れながら、貧困地域の子ども支援・炊き出し・海上スラム訪問・交流に取り組み、国際理解と自律性を育てます。
春休みは2026年3月23日から1週間(6泊7日)を3コースで募集します。
春・夏の受入情報/資料
- ZOOM説明会のお知らせ(春休み向け)
- セブプログラム デジタルパンフ(PDF)
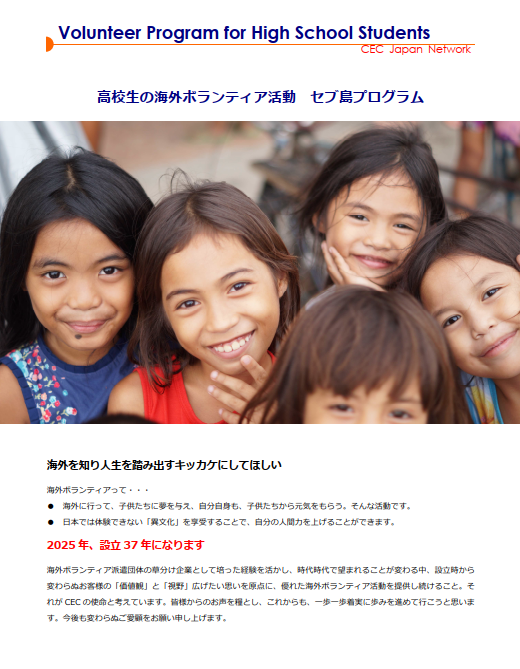
AndroidではPDF内リンクが反応しない場合があります。
Google Playから「Adobe Acrobat Reader」をご利用ください。

貧困地域の子ども支援(教育・炊き出し・交流)
高校生が個人参加で現地ではグループ活動するプログラム。1週間(6泊7日)で、セブ市内のスラムや山村集落・海上スラムなどで子どもたちと交流し、学びと成長を体験します。高校生主体の参加設計です。
セブには、貧困層の子どもや家族を支援する複数のNGOがあります。本プログラムでは、教育支援・食事提供(炊き出し)・コミュニティ訪問・聞き取りなどを通じて現状理解を深めます。希望者には参加証明書を発行します。
活動のポイント
ストリートチルドレン支援、山村のリロケーションサイト訪問、海上スラムでの教育交流などを予定。天候等により屋外活動が中止・変更となる場合があります。柔軟な気持ちでご参加ください。
※ 日本人スタッフと現地フィリピン人スタッフの2層サポートで安心。
※ 可能であれば夏物の古着寄付にご協力ください(現地NGOへ寄贈)。
春・夏休み|高校生一般募集(2026年春)
2026年春休み:1週間(6泊7日)の受入れ。出発日は3/23(月)、3/26(木)、3/29(日)。
参加費用のページ
第一班:3/23(月)- 3/29(日)
第二班:3/26(木)- 4/01(水)
第三班:3/29(日)- 4/04(土)
活動スケジュール(例:6泊7日)
| 日 | 午前 - 午後 |
|---|---|
| 1 | 日本各地からご出発(セブ着) |
| 2 | AM:オリエンテーション/バディと文化交流 PM:教会周辺で物売りをする子どもたちを把握、スナック提供活動 .jpg)
.jpg)
※ 時期によりスケジュールは変動します。 |
| 3 | 山村のリロケーションサイト訪問(生活の聞き取り・炊き出し)
.jpg)
.jpg)
市内スラムの交流と炊き出し活動も行います。 .jpg)
.jpg)
楽しい時間の提供も大切な活動の目的です。 |
| 4 | 終日自由行動:海・山のツアー/市内見学/ボランティア同行可


ZIPライン・山の魅力・コーヒー農園訪問など学べるツアーも。 

市街近郊の海は濁りがあるため、離島/南部方面がおすすめ。 |
| 5 | 海上スラム訪問(教育交流・コミュニティ聞き取り)
.jpg)
.jpg)
アクセサリー制作など生活のための生産手段にも触れます。 |
| 6 | セブ最大規模のゴミ山スラム訪問/振り返り


最低賃金未満の収入や生活の実情を住民から直接伺います。 |
| 7 | 帰国の途につきます。 |
| ※ 天候・現地都合により変更あり。 |
バディと話そう、一緒に活動しよう!
プログラム期間中は、現地の高校生や大学生が「バディ」としてみなさんと一緒に活動を共にします。彼らは、小さな頃から私たちが教育支援を行ってきた子どもたちで、貧困の中で育ちながらも、自分の夢や目標に向かって懸命に努力している、前向きで力強い若者たちです。
バディとのコミュニケーションは英語になりますが、わからないことがあれば遠慮なく何度でも聞き返してください。会話を重ねる中で、彼らの背景や思いに触れ、フィリピンの人々がどんな価値観を持ち、どんな未来を描いているのかを知る貴重な機会になります。そして、私たちに何ができるのか、一緒に考える時間にもなるはずです。
バディ制度:現地高校生・大学生と英語で交流
期間中は、現地の高校生・大学生がバディとして同行。英語での交流を通じて相互理解を深めます。困った時は日本語サポートも可能です。
Buddies
スラム・墓地・山村など厳しい環境で育ちながらも、奨学金などで進学に挑む若者たちです。
.jpg)
.jpg)
英語で対話を重ね、価値観の違いを学び合います。
宿泊:市内ホテルで安心・快適
治安と衛生環境に配慮し、市内ホテルに滞在。温水シャワー・エアコン・テレビ完備。高校生は原則2名1室。毎朝朝食つき。
初めての海外ボランティア 高校生の声
春休み参加 1週間滞在
セブと聞くとリゾートやビーチをイメージしていたが、その裏には過酷な環境で生活している人もいるということを目の当たりにし、貧困格差を改めて考えさせられた。
しかしスラムに住む方達はみんな笑顔で優しく子供たちもとても元気で私なんかよりもずっと幸せそうに見えた。幸せとはなにか幸せのあり方というものを考えるよいキッカケになった。日本は発展しすぎていて当たり前の基準がとても高くなっている上、幸せに気づきにくいなとセブに行って感じた。自分の暮らしを当たり前と思わず何事にも感謝できる人間になりたいと強く思う。
スラムの子達は私のたどたどしい英語もしっかり聞いてくれたり、たくさん質問をしてくれたり、母語ではない英語を使って一生懸命話してくれたことがとても嬉しく印象に残っている。
みんなパワフルなので暑くて少しハードだったけど、あの子達と過ごした時間や学びは一生忘れない良い経験になったと思う。ボランティア以外でもモールの警備さんやタクシーの運転手さんなどと会話したりタガログ語を教えてもらったり、セブの人はみんなフレンドリーで優しい人ばかりだった。
道や車の整備、トイレや水道問題などは日本に比べてしまうと良い環境とはいえないが、1週間過ごすとその環境にすら慣れたので、初め抱えていた不安などはすっかり無くなった。食べ物も美味しく、暑いけど良い天気で、人々もとても優しく陽気でこちらまで元気をもらえるようなそんな素敵な国だった。
スラムの子達から学んだこと、セブ島の生活から学んだこと、たくさん日本と違うところがあったけどどれも自分の人生の価値観を大きく変える良い経験となった。必ずまたセブ島に行きたい。
…‥・゜+.*・‥…☆。゜+.*…‥・゜+.*・‥
3週間の高校生ボランティア(トビタテ留学生)の皆さまの体験感想
■活動から感じたこと 20日間いた、その20日間が15年しか生きてはいませんが自分史上「最速」の20日間であったこと、それが今痛感していることです。子供たちに癒され、フィリピンの人たちの優しさを日々強く感じ、とてものびのびとした、そして充実した20日間であったと感じています。日本との違いはやはり「人の中身」だと思います。あくまで僕の考えなのですが、やはりフィリピンの人、セブの人は「自分」を強く持っている気がしました。
日本では合わせなければいけないかもしれないのですが、「自分は自分」という考えをちょこちょこ感じることができました。そういったところがいい意味での「頑固さ」であると思います。あと感じたのは何かゆるいということ。 僕はPalazzoに宿泊していたのでAyala によく行っていたのですが忘れて、警備体制はモールに入るときに荷物チェックなどと日本でよりも上じゃないかな?と思う時がしばしばありました。ただたまに「君はいい」みたいな感じでスルーしたりして「えっ、意外とゆるいな」とか街を見ていても「このブロックはちゃんとしたビルやのに横は簡易的というかスラムにあるような家が3棟ぐらい集まってできてるブロックやな」などそういうところは日本よりかは縛られていないような、ある意味で「自由度が高い」などは思いました。
この「頑固さ」と「自由度の高さ」というのが日本との違いだと僕は感じましたし、それが外国の人の「積極的」とか「フレンドリー」みたいなところの根源にあるのではないかなと思いました。
■来年参加するトビタテ留学生へのメッセージ
いろんな家族がセブにはいて、すごく狭い家に5人で寝てる、10人で寝てる…聞いて耳を疑うようなこともあります。
ただそれが現状であるということでありそれをどうにかするためにいれるのは今年は20日間だったのですが、短い期間で何回来れるかわからなくても、一回一回精一杯心の支えになり、生活の支えになり、現状を知り、そしてそれを伝えるそれが伝達者「ambassador」としての役目であり、「トビタテ」であり、「CEC ボランティアの一員」なのです。
僕は15歳でトビタテに受かり参加しました。しかし、このトビタテに受からなくても行く価値のあるボランティア活動であると思います、僕らは(日本という)世界のなかで治安でも経済でも衛生環境も一番上で生活をしている、そういっても過言ではないと思います。 それがはたして人にとってプラスなのか?犯罪も少なく、貧困に大半の国民が瀕しているわけでもなく、飢えもなく、危機感のない生活を送ることこそが本当にプラスなのか考えた時、受かっても受かってなくても、あくまで私個人の感想ですし意見なのですが、参加すべきものだろうと、帰国して便利であり、キレイであり、危機感のないそんなことと思いはじめて考えました。




